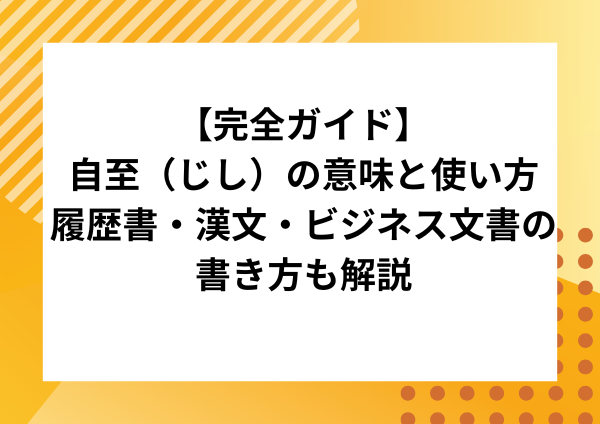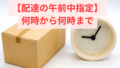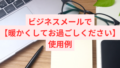この記事では、「自至(じし)」という表現の正しい意味や使い方を、初心者にも分かりやすく丁寧に解説します。履歴書・契約書・漢文・ビジネス文書など、さまざまな場面で使われるため、知っておくと非常に役立つ言葉です。
特に正式な文書では誤用が多いので、このページでしっかり理解しておきましょう。
自至(じし)とは?意味&読み方

「自至(じし)」は、
自(〜から)+ 至(〜まで)= 〜から〜まで
という期間・範囲を示す正式な表現です。読み方は じし(じ・し)。
古くから文書表現として使われ、現在も以下のような場面で活躍しています。
- 履歴書・職務経歴書
- 契約書・規約・報告書
- 交通費申請や通勤経路の記載
- 漢文・古典の授業
フォーマル度が高く、文章を簡潔かつ正確に伝えるための便利な表記です。
言葉の由来と漢文での使い方

「自至」は 中国古典(漢文)由来 の表現です。漢文では、
- 自〇〇 至〇〇(〇〇から〇〇まで)
の形で使われ、年表・歴史書・記録文で非常に重要な役割を果たしてきました。
● 漢文での例
- 自春 至夏 … 春から夏まで
- 自東京 至大阪 … 東京から大阪まで
- 自元年 至五年 … 元年から五年までの期間
日本にもそのまま伝わり、明治以降の官庁文書・教育現場で広く浸透してきました。現在でも「正式な文書の書き方」として定着しています。
実践!自至の書き方(履歴書・文書・通勤記録など)

◆ 履歴書での自至の使い方
履歴書では、学歴・職歴の期間を示すために用いられます。
自2020年4月 至2023年3月 ○○大学卒業
自2023年4月 至現在 △△株式会社勤務
ポイント:
- 「至現在」を明記する(在職中が明確になる)
- 和暦・西暦は 必ず統一
- 年月の抜けや誤記に注意
◆ ビジネス文書での自至
契約書・報告書などで業務期間や有効日を示す際に使用されます。
例:
契約期間:自2025年4月1日 至2026年3月31日
研修期間:自2024年5月1日 至2024年6月30日
必要に応じて「更新あり」などの補足を付ける場合もあります。
◆ 通勤経路・交通費申請での使い方
自横浜駅 至新宿駅
自大宮駅 至渋谷駅(△△駅経由)
経由駅を書くとより丁寧で伝わりやすくなります。
よくあるミスと注意点

❌ 1. 「自」と「至」の順番を逆にする
→ 意味が崩れ、誤解の原因に。
❌ 2. 「2020.4〜2023.3」などの省略表記はNG
→ 公式文書では必ず 自〇年〇月 至〇年〇月 と書く。
❌ 3. 在職中なのに「至現在」を書かない
→ 継続か終了かわからず不正確。
❌ 4. 和暦と西暦を混在させる
→ 一貫性がないと不親切な印象に。
❌ 5. 年月の入力漏れ・誤字
→ 文書の信頼性を損なうため最終確認は必須。
Q&A:こんな場合どう書く?

Q1. 在職中の職歴は?
A.「自2022年4月 至現在」 と書くのが正解。
Q2. 年号は西暦と和暦どちらがいい?
A. どちらでもOKだが必ず統一。 迷ったら西暦が無難。
Q3. 日付は日まで必要?
基本は 年・月で十分。契約書などは日付まで必要なことも。
Q4. 部署異動があった場合は?
異動前後で分けて書きます:
自2020年4月 至2022年3月 営業部
自2022年4月 至現在 総務部
Q5. 学歴・資格取得でも使う?
A. はい。期間を示す場合は「自至」で明確になる。
まとめ:自至を正しく使うポイント
- 自至= 〜から〜まで を示す正式表現
- 由来は漢文で、現代の履歴書・契約書でも現役
- 基本形は 自〇年〇月 至〇年〇月
- 在職中は 「至現在」 を忘れずに
- 省略や誤記は信頼性ダウン、丁寧さが重要
「自至」を正しく使いこなせると、公的文書・履歴書・ビジネス文書がぐっと読みやすく、正確になります。あなたの文章の印象も大きく向上しますので、ぜひ今日から実践してみてくださいね。