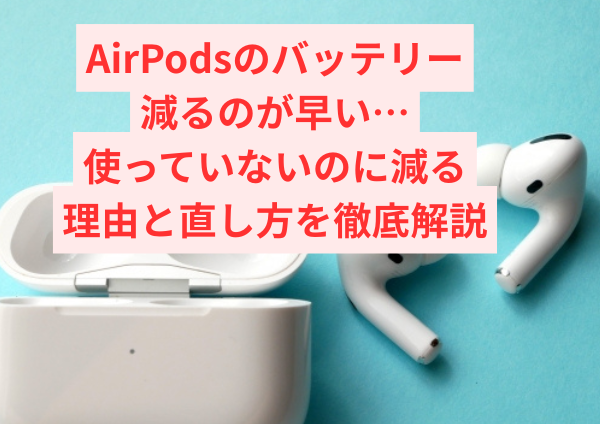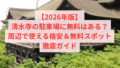AirPodsを使っていないのに充電が減るのはなぜ?(まず知りたい結論)

どれくらい減ると“異常放電”?正常な減り方の目安
AirPodsは使っていなくても、1日に数%ほどバッテリーが減ることがあります。これは電子機器全般に見られる自然な現象です。ただし、朝100%だったのに夕方には80%以下になっている、というような“目に見えて減っている感覚”がある場合は注意が必要です。特に、10〜20%以上の急激な減少が続く場合は、異常放電や内部的なトラブルが起きている可能性が高くなります。また、減り方が毎日バラバラだったり、片方だけ極端に減る場合も異常のサインです。
まず確認したい「自然放電」ととは?
電子機器は電源を入れていなくても、内部の制御チップや通信機能が微弱に電力を消費します。AirPodsも同じで、ケースに入れている間でも“完全にゼロ消費”になることはありません。特にAirPodsは常にデバイスとの通信準備をしているため、わずかな放電が発生します。とはいえ、通常の自然放電であれば1日あたり3〜5%程度が目安で、それ以上の減り方が続く場合は別の原因が考えられます。
ケースに入れていてもBluetoothが繋がる理由
AirPodsは、ケースに収納されていてもiPhoneの近くにあると「いつでも接続できる待機状態」になります。この待機状態では、完全に電力をオフにするわけではなく、通信の準備をするために微量のバッテリーを消費します。また、近くに複数のApple製品があると、それぞれと接続しようと確認を行うため、自然放電が増えることもあります。特にWatchやiPadを併用している方は、ケースにしまっているだけでも消費が早く感じる原因になりやすいです。
バッテリーの劣化・寿命が原因になるケース
長期間使っていると、AirPods内部のリチウムイオン電池が少しずつ劣化し、電力を蓄えられる容量が減っていきます。特に毎日のように充電と放電を繰り返している場合、バッテリーは徐々に弱っていき、購入当初よりも放電が早く感じられるようになります。また、通勤や外出時に気温差の激しい環境にさらされることで、劣化が加速することもあります。一般的には2〜3年以上使っている場合に症状が出やすくなりますが、使用頻度が高い方は1年半ほどで劣化を感じることもあります。最近、急に電池持ちが悪くなったと感じるなら、一度劣化を疑ってみてもよいでしょう。
ケースや端子の汚れ・接触不良が影響することも
イヤホンとケースの接点が汚れていると、正しく充電されず結果的にバッテリー残量が減り続けてしまうことがあります。糸くずや皮脂、ホコリなどが少し付着しているだけでも、接触が不安定になり「充電されたと思っていたのに実はされていなかった」という状況が起こりやすくなります。また、カバンの中でケースが振動したり、イヤホンがズレたりすると、充電が途中で止まってしまうことも。定期的に柔らかい布や綿棒で軽く掃除し、異物を取り除くことで改善するケースが多いので、まずは簡単なお手入れから試してみるのがおすすめです。
AirPodsの充電が減る原因チェックリスト

端子の汚れ・イヤホンがケースに奥まで入っていない
接触不良はAirPodsの電池が減る原因としてとても多く、見落としがちなポイントです。ケース内部の端子にホコリや皮脂が付着していると、充電が途切れたり弱くなったりし、結果としてバッテリーがどんどん減っていく状態につながります。また、イヤホンがケースにしっかり奥まで入っていないと、見た目では“充電されているように見える”のに、実際には接点が触れておらず充電ができていないこともあります。毎日使うアイテムだからこそ、知らないうちにゴミが溜まりやすいため、週に1度程度の簡単な掃除で予防するのがおすすめです。
iPhone側の不具合・古いiOS
iPhoneのiOSが古いままだと、Bluetooth接続が安定せず、AirPods側が「接続し直そう」と何度も通信を試みるため、余計な電力消費につながることがあります。特に、メジャーアップデートや不具合修正が含まれるバージョンを長期間適用していない場合は、この影響が大きく出やすいです。また、iPhone自体の動作が不安定になり、AirPodsとの通信が途切れたり復旧したりを繰り返すことで、気づかないうちにバッテリーが消耗することもあります。最新の状態に更新することで改善するケースが多いので、定期的なアップデート確認はとても重要です。
自動接続(Apple Watch・iPad・Mac)による電力消費
複数のAppleデバイスを持っていると、AirPodsは常に「どのデバイスに接続すべき?」とバックグラウンドで判断を続けています。この自動切り替え機能は便利なのですが、その分バッテリーを消費しやすいという側面もあります。たとえば、自宅にiPadとMac、外出時にはApple WatchやiPhoneがある場合、AirPodsは常に周囲のデバイスを確認し続け、最適な接続先を探す処理を行っています。これが積み重なることで、使っていない時間でも電池が減りやすくなるのです。必要に応じて自動切り替えをオフにすると改善することがあります。
ファームウェアが古いと電力消費が増える?
AirPodsは基本的に自動でファームウェア更新が行われますが、必ずしも最新になっているとは限りません。古いファームウェアにはBluetooth接続の不具合やバッテリー消費が大きくなる問題が残っている場合もあり、そのまま使い続けると無駄な電力消費につながることがあります。また、ケースに入れて充電器につないでいても、iPhoneの近くに置いていないと更新されないこともあるため、意外と更新が止まっていることがあります。時々バージョンをチェックし、必要に応じて更新される環境を整えることでバッテリー持ちが改善する可能性があります。
ケースの蓋の開閉が多いと電池が減る理由
ケースを開けるたびにAirPods内部のチップが起動し、デバイスとの接続準備を行うため、想像以上にバッテリーを消費します。特に「ちょっと確認するだけ」のつもりで何度も蓋を開け閉めすると、そのたびにAirPodsが起動→待機状態に入るというサイクルが繰り返され、知らないうちに電池残量が大きく減ってしまうことがあります。また、蓋を開けている時間が長いほどAirPodsがアクティブ状態を維持する時間も長くなり、自然放電のスピードが早まる原因にもなります。普段から「必要なときだけ開ける」ことを意識するだけでも、バッテリーの消耗を抑える効果があります。
磁力の弱まりで充電が安定しないことがある
長く使い続けるとケースの磁石が弱くなり、イヤホンがうまく固定されずに微妙な隙間が生まれてしまうことがあります。この隙間が原因で充電が途中で止まってしまったり、「充電されているように見えて実はされていなかった」という見落としが起こることも増えます。また、磁力が弱くなるとイヤホンがケース内でわずかに動いてしまい、振動だけで接点が外れるケースもあります。外出時のバッグの中やポケットの中で起きる小さな揺れでも充電が妨げられることがあるため、購入から時間が経っている場合はとくに注意が必要です。さらに、汚れの付着や金属疲労も磁力低下につながるため、定期的な清掃とチェックを行うことで充電ミスを防ぐ確率が高くなります。
AirPods Pro特有の電池消費の理由(Proユーザー向け)

アクティブノイズキャンセリングによる電力消費
ANC(アクティブノイズキャンセリング)は、周囲の騒音を消して快適なリスニング環境を作るとても便利な機能ですが、そのぶん内部で高度な処理が行われているため、電力消費が大きくなりやすいという特徴があります。特に通勤・通学の電車内やカフェなど、常に騒音がある環境で使っていると、AirPodsは周囲の音を細かく分析し続ける必要があり、その負荷がバッテリーの消耗につながることがあります。さらに、ANCを長時間オンにしたまま使い続けると、AirPodsがほんのり温かくなることもあり、これも電力消費が増える一因になります。必要のない場面ではANCをオフにしたり、外部音取り込みモードに切り替えることで、電池持ちを大きく改善できる場合があります。
外部音取り込みモードとの違い
外部音取り込みモードも周囲の音をマイクで拾いながら再生するため電力を使いますが、ANCほど複雑な処理を行わないため、比較するとバッテリー消費がやや少なくなる傾向があります。しかし、完全に節約モードというわけではなく、環境によっては音量調整や外音の取り込み処理などが頻繁に行われ、そのぶん電力を使うこともあります。たとえば、風が強い場所や人の声が多い場所では処理が多くなり、結果として消費が増えることがあります。状況に応じてオン・オフを調整し、自分の生活シーンに合わせて使い分けることで、より効率的にバッテリーを節約できます。
Proモデルだけ起きやすい接続不具合
AirPods Proは複数のマイクや高度なチップを搭載しているため、他のモデルよりも繊細で高性能です。そのぶん、接続状況が不安定になるとBluetoothを再接続しようと内部で処理を繰り返し、気づかないうちにバッテリー消費が増えてしまうことがあります。また、iPhone側の通信状態が悪い、周囲に多くのBluetooth機器があるなどの状況では、接続が揺らぎやすく、AirPodsが常に「最適な接続先」を探し続けてしまうこともあります。こうした現象はトラブルと気づきにくいため、Proモデルを使っていて電池の減りが妙に早いと感じるときは、一度リセットや再接続を試してみると改善しやすくなります。
AirPodsの発熱と電池消費の関係

気温差で電池が減って見える現象
特に冬は気温差でバッテリー残量が急に減ったように見えることがあります。寒い場所ではリチウムイオン電池の動きが鈍くなり、実際の残量よりも少なく表示されることがよくあります。たとえば、屋外に出た瞬間に残量が一気に下がったように見えても、室内の暖かい環境に戻ると数%回復することもあります。この現象は不具合ではなく温度による一時的な変化で、特に冬場や冷房の強い場所で起こりやすいです。気温差が大きい季節は、ポケットの中やバッグの内側など、できるだけ温度変化の少ない場所に入れておくと電池の表示が安定しやすくなります。
ケースが熱くなると減りが早い理由
高温環境では電池の劣化が進みやすく、消費も早くなります。AirPodsのケースは小型ながら内部にバッテリーが入っており、発熱が続くと内部温度が上昇してしまいます。スマホと同様、バッテリーは熱に弱く、熱を持つと電池の消耗スピードが一気に上がります。さらに、熱をもった状態が続くとバッテリーそのものの寿命が短くなってしまうため、日差しの強い車内や充電しながら布に包んで放置するなどの“熱がこもる状況”は避けるのが安心です。また、ワイヤレス充電は有線よりも発熱しやすいため、電池の減りが気になる時期は有線に切り替えると安定しやすくなります。
放置中の発熱は要注意?
何もしていないのに熱を持つ場合は不具合の可能性があります。本来、AirPodsは待機中に熱を持つことはほとんどなく、触ってわかるほど温かい場合は、内部でBluetoothの再接続やスキャンが繰り返されている可能性があります。また、ケース内部のチップにエラーが起きていたり、ファームウェアの不具合で異常に動作し続けているケースもあります。軽い発熱なら一度リセットすることで収まることがありますが、継続して熱くなる場合は内部トラブルのサインです。Appleサポートで診断してもらうと早期解決につながるため、気になる場合は早めに相談するのがおすすめです。
AirPodsの充電が減るときに今すぐ試したい対処法

Bluetooth接続を一時的にオフにする
一度Bluetoothを切ることで、不要な接続をリセットできます。特に、複数のAppleデバイスを使っている方は、AirPodsがあちこちに接続しようとして負荷がかかっていることがあります。一時的にBluetoothをオフにすることで、AirPodsの動作が落ち着き、余計なバッテリー消費が止まることがあります。数秒後にオンに戻すだけで改善することもあるため、まず最初に試したい簡単な対処法です。
ケースとイヤホンの接点を掃除する
綿棒や柔らかい布で軽く拭くだけでも効果があります。特に、皮脂やほこりは見えにくく、少し付着しているだけで接触不良の原因になります。接点部分にゴミが溜まっていると、AirPodsが「充電されていない」と認識して、接続を探し続ける動作が起こり、結果として電池の減りが早くなることもあります。丁寧に掃除することで、充電効率も改善し、バッテリー消費の無駄が減ります。
iOSアップデートとファームウェア更新を確認
最新状態にしておくことで安定性が向上します。古いiOSやファームウェアには、Bluetooth接続が不安定になる不具合が残っていることがあり、それが原因でAirPodsが何度も接続を試みてしまうことがあります。これがバッテリーの異常な消耗につながるため、定期的なアップデートは非常に重要です。更新することでBluetoothの挙動が安定し、バッテリー持ちが改善されたという声も多いです。
AirPodsをリセットして接続をリフレッシュ
一度リセットして再設定すると改善されやすいです。AirPodsの内部設定が乱れていると、持続的に接続処理を行ってしまい、バッテリー消費が増える場合があります。リセットすることで内部データが整理され、接続トラブルが改善されることがあります。方法も簡単で、ケース背面のボタンを長押しするだけなので、電池の減りが目立つときはぜひ試してみてください。
iPhoneの「ネットワーク設定リセット」も有効
通信関連のトラブルを解消してくれる場合があります。ネットワーク設定をリセットすると、Wi‑FiやBluetooth、モバイル通信などの接続情報が初期化されるため、内部で起きていた“見えないトラブル”がクリアになることがあります。AirPodsが何度も再接続を繰り返して電池を消耗していた場合、このリセットによって動作が安定するケースはとても多いです。ただし、Wi‑Fiのパスワードなどもリセットされるため、事前に控えておくと安心です。操作は数分で終わるので、バッテリーの減りが急に早くなったときの有力な対処法のひとつです。
Appleサポートでバッテリー診断・交換依頼する方法
寿命が近い場合はプロに相談しましょう。Appleサポートでは、AirPodsのバッテリー状態を確認してもらえるほか、必要に応じて交換サービスも受けられます。特に2〜3年以上使っている場合は、内部バッテリーが劣化している可能性が高いため、プロの診断を受けることで原因がはっきりし、安心して使い続けることができます。また、交換費用やサービス内容はモデルによって異なるため、事前にオンラインチャットや電話で相談するとスムーズです。
AirPodsのバッテリーを長持ちさせる3つの習慣

「バッテリー充電の最適化」を有効にする
iPhoneがあなたの使い方を学習し、バッテリーにやさしく充電してくれます。この機能をオンにしておくと、普段の使用習慣をもとに80%まで充電した後、一気に100%まで充電せず、必要な時間帯に合わせてゆっくり満充電にしてくれるため、バッテリーへの負荷が大幅に軽減されます。また、夜に充電して朝まで差しっぱなしにすることが多い方にとっては特に有効で、無駄な過充電を防げるため、長期的なバッテリー寿命の維持にとても役立ちます。
過充電・過放電を避けるコツ
残量0%や100%の状態を長く続けないことが大切です。リチウムイオン電池は極端な状態に弱く、どちらの状態も続くと劣化を早めてしまいます。50〜80%の範囲で保つのが理想的ですが、日常でそこまで厳密に管理するのは大変なので、「完全にゼロまで使わない」「100%のまま長時間放置しない」という点を意識するだけでも効果があります。また、外出前に短時間だけ追加で充電する“ちょい足し充電”もバッテリーに優しい方法です。
高温・低温を避けた保管方法
直射日光や寒すぎる場所を避けるだけで寿命が変わります。特に夏は車内や窓際、冬は外気に長く触れるなど、急激な温度変化によってバッテリーに負荷がかかることがあります。AirPodsは小型で熱がこもりやすいため、温度の影響を受けやすいのが特徴です。バッグの外ポケットなど、気温の影響を受けやすい場所より、内側のポケットやケースに入れておくほうが安心です。また、使わない期間が続く場合は、40〜60%程度の残量を保った状態で保管すると、劣化を最小限に抑えることができます。
ケースを開けっぱなしにしない工夫
無意識に開けてしまいがちな人は、意識して閉めておきましょう。ケースを開いたままにするとAirPods本体がアクティブ状態になり、内部チップが待機モードに入るため、本来必要のないバッテリー消費が発生します。また、ホコリやゴミが入り込みやすくなり、端子の汚れによる接触不良にもつながる可能性があります。とくにバッグの中や机の上に置きっぱなしにすると開いたままになりがちなので、こまめに閉じる習慣をつけることで、バッテリーにも衛生面にもプラスになります。
AirPodsの電池が減りやすい人の共通パターン

毎日長時間接続している
使いすぎも電池の消耗を早めます。特に、通勤や通学中ずっと音楽を流し続けたり、在宅中にBGM代わりに長時間つけっぱなしにしていると、AirPods内部のバッテリーは休む暇なく働き続けることになります。また、頻繁に接続と切断を繰り返すような使い方も負荷がかかりやすく、結果としてバッテリー劣化が通常より早まるケースがあります。「気づいたら1日中つけていた」という方は、たまに耳から外して休ませる時間をつくることでバッテリー負担を軽減できます。
ワイヤレス充電を多用している
便利ですが発熱しやすく、バッテリー寿命が縮むことも。ワイヤレス充電はコードの抜き差しが不要でとても手軽ですが、充電中にケースが熱を持ちやすいというデメリットがあります。バッテリーは熱に弱いため、発熱が繰り返されると内部の劣化が進みやすくなり、結果として電池持ちが悪くなります。また、ワイヤレス充電器の種類や配置によっては、わずかなズレで充電効率が落ち、充電時間が長くなることで発熱が増えるという悪循環が起こることも。電池の減りが気になっている時期は、できるだけ有線充電を活用するのがおすすめです。
片方だけ接続されている状態になっている
片耳だけ消費が激しい場合があります。AirPodsは左右が独立して動作できるため、片方だけがデバイスに接続されたままになることがあります。たとえば、片耳で電話した後にもう片方をケースに戻し忘れたり、単独モードで使用してそのままにしてしまった場合などです。片方だけがBluetooth接続を維持し続けると、その分バッテリー消耗が早くなり、左右の残量に大きな差が出ることがあります。左右どちらもケースにしっかり入っているか、使用後に確認する習慣をつけると防ぎやすくなります。
ケースに戻し忘れが多い
バッグやポケットに放置しないよう注意しましょう。AirPodsをケースに戻さずポケットに入れたまま歩いたり、テーブルに置いたまま忘れてしまうと、実はその間もわずかに電力を消費し続けています。ケースに戻さない状態では自動で電源オフにならないため、内部チップが待機モードを続け、気づかないうちにバッテリーがどんどん減ってしまうことがあります。また、ポケットやバッグの中で誤作動し、意図せず再生が始まってしまうケースも。使用後は必ずケースに戻すという習慣をつけるだけで、電池の消耗を大幅に抑えることができます。
実例紹介|バッテリー消費が改善した人のケース集

ケース掃除で改善した例
ちょっとした汚れが原因だったという声は多いです。実際、端子部分にほこりや皮脂がわずかに付着していただけで充電がうまくできず、結果として”勝手に減っているように見えていた”ケースはとても多いです。掃除後は一気に安定したという声もあり、もっとも手軽で効果が出やすい改善方法といえます。
iOS更新で改善した例
古いOSのままだと不具合が起きやすいことも。特にBluetooth関連のバグはアップデートで修正されることが多く、更新しただけで接続トラブルが解消し、バッテリー消費が落ち着いたという例がたくさん報告されています。「減りが急に早くなった」タイミングがiOS更新前と重なる人は、まずアップデートを試す価値があります。
リセットで直った例
リセットは簡単で効果的な方法のひとつです。内部設定の乱れでBluetoothが何度も再接続を繰り返しているような状態では、AirPodsは通常より多くの電力を使ってしまいます。リセット後にスムーズに接続されるようになり、バッテリー持ちが大きく改善したケースも非常に多いです。
買い替えで大幅改善した例
古いモデルを使っている場合は買い替えで劇的に改善することもあります。特に2〜3年以上使用しているAirPodsはバッテリー劣化が進んでいる場合が多く、新しいモデルに変えることで「同じ使い方でも電池が倍以上持つようになった」という声もあります。最新モデルは省電力機能も強化されているため、長期的に使うなら買い替えは大きなメリットになります。
それでも電池が減るときは?買い替えの判断基準

バッテリー交換すべき症状
突然のシャットダウンや残量の急減が目立つ場合は交換を検討しましょう。たとえば、朝は80%あったのに数分使っただけで30%まで落ちてしまう、片耳だけ急激に減る、数分の音楽再生で電源が切れてしまうなどの症状が続く場合は、バッテリーの劣化がかなり進んでいるサインです。また、温度変化のない室内で使用しているのに異常な減り方をする場合や、リセット・掃除・アップデートを行っても改善しない場合も、交換のタイミングとして判断しやすいポイントです。放置するとさらに劣化が進むため、早めの対応がおすすめです。
本体買い替えのタイミング
2〜3年以上使っていて電池持ちが悪いなら買い替え時です。AirPodsのバッテリー寿命は使用頻度にもよりますが、約2年で体感できるほど劣化してくることが多く、「フル充電しても1〜2時間しか持たない」「片方だけ極端に減る」「ケースの充電もすぐなくなる」といった状態が続く場合は、本体そのものの交換を検討しても良い時期です。さらに、最新モデルは音質・ノイズキャンセリング性能・接続の安定性などが大きく向上しているため、買い替えによってストレス軽減や使い心地の改善を感じやすいというメリットもあります。
AirPods(第2/第3世代・Pro・Max)を比較
用途や好みに合わせて選びやすいよう特徴をまとめます。第2世代は価格が手ごろで軽量なのが魅力、第3世代は空間オーディオ対応で立体的な音が楽しめます。Proモデルはノイズキャンセリングと外部音取り込みが優秀で、外出先での快適さが段違いです。Maxはオーバーイヤー型ならではの高音質・長時間使用向けで、自宅でじっくり音楽を味わいたい人に最適です。それぞれ得意とするシーンが異なるため、自分のライフスタイルに合ったモデルを選ぶことが重要です。
用途別のおすすめモデル
普段使い・通勤・運動など目的に合わせて選びましょう。たとえば、通勤やカフェで集中したい人にはAirPods ProのANCがぴったり。音楽を自然に楽しみたいなら第3世代、軽快に使いたい人や初めてのAirPodsには第2世代が扱いやすいです。自宅で高音質を楽しみたい、映画やゲームをより迫力ある音で体験したいならAirPods Maxが良い選択になります。また、運動がメインの場合は、フィット感が安定しやすいProシリーズが特に人気です。自分の生活シーンと求める性能を照らし合わせて選ぶと、より満足度の高い買い物ができます。
よくある質問(FAQ)

AirPodsを使っていないのに1日で20%減るのは正常?
20%以上減るなら異常放電の可能性があります。通常の自然放電であれば1日あたり3〜5%ほどの減少に収まることが多く、10%前後でも環境や使い方によっては許容範囲です。しかし、20%以上の大幅な減少が毎日のように続く場合、内部でBluetoothのスキャンが繰り返されていたり、ケースや本体の接触不良が起きていたりと、何らかのトラブルが発生している可能性があります。また、寒暖差の激しい環境で保管している場合にも減りが早く見えることがあるため、まずは使用環境の見直しや簡単な対処法から試してみると安心です。
ケースだけ充電が減るのはなぜ?
ケース内の通信機能が電力を使うことがあります。AirPodsのケースは小さいながらも内部にチップが搭載されており、iPhoneなどのデバイスとの通信準備やバッテリー管理のために常に微量な電力を消費しています。また、蓋の開閉によって内部がアクティブになるため、頻繁に開け閉めすると電力消費が増える傾向があります。さらに、AirPods本体が正しく収まっていないと充電がループしてしまい、ケース側の電池が減り続けることもあります。こうした動作は意外と見落とされがちですが、ケースだけ減る現象のよくある原因です。
AirPodsは100%充電のまま放置しても大丈夫?
長期間続けると劣化しやすいので避けましょう。リチウムイオン電池は満充電の状態を長く維持するとバッテリーに負荷がかかり、劣化が進みやすい特徴があります。毎日寝る前に充電して朝まで差しっぱなしにする習慣がある場合は、知らないうちにバッテリー寿命を縮めている可能性があります。とくに高温環境では劣化が加速するため、充電後は速やかにケーブルを外すか、「バッテリー最適化」などの機能を活用して負担を軽減することが大切です。短いスパンでこまめに充電するスタイルに切り替えるだけでも、長く快適に使いやすくなります。
80%充電の方が寿命が伸びるって本当?
はい、リチウム電池は80%前後がもっとも安定します。リチウムイオン電池は満充電やゼロに近い状態を特に苦手としており、常に100%をキープし続けたり、0%まで使い切ったりすると、内部の化学反応がダメージを受けやすくなります。そこで、多くのメーカーが推奨しているのが「80%前後で保つ」という運用方法です。これはバッテリーの負担が最も少なく、劣化スピードを遅らせる効果が期待できるためです。また、普段の使い方としても、80〜90%あれば日常利用には十分であり、こまめに短時間充電するスタイルのほうが長寿命に繋がりやすくなります。
ワイヤレス充電と有線充電どちらが減りにくい?
発熱の少ない有線充電の方がバッテリーには優しいです。ワイヤレス充電は便利ですが、充電中に発熱しやすいという特徴があります。バッテリーは熱に弱く、特に高温状態が続くと劣化が早まってしまうため、電池持ちが気になっている時期には有線での充電をメインにする方が安心です。また、有線充電はケーブルが直接接続されるため電力ロスが少なく、より安定した速度で効率よく充電できます。長期間にわたってAirPodsを大切に使いたい人にとって、有線充電をうまく取り入れることはバッテリーケアの大きなポイントになります。
まとめ|AirPodsのバッテリーを正しくケアして長く使おう

AirPodsは少しの工夫でバッテリーを長持ちさせることができます。毎日のちょっとした使い方を見直すだけでも、電池の減りが驚くほど安定しやすくなりますし、結果として本体の寿命そのものもぐっと伸ばすことができます。また、清掃や設定の見直しなども特別な道具はいらず、その日のうちにできる簡単なケアばかりです。普段から丁寧に扱うことで、快適に長く使えるので参考にしてみてくださいね。