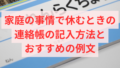刺身とともに提供される大根の千切り、皆さんはどうされていますか?
食べる人もいれば残す人もいますよね。
インターネット上ではどっちにするか意見が分かれ、「さっぱりとして美味しい」と食べる人もいれば、「あまり食べたくない」「水っぽい」と感じる人もいるようです。
それでは、マナーとしては食べるのがいいのでしょうか?残してもいいのでしょうか?
この記事では、そのマナーについて紹介します。
刺身に添えられる大根千切りの意味と歴史

刺身に添えられる大根千切りは、「つま」とも呼ばれ、盛り付けを美しく見せる役割を担います。
特に大根の使用が一般的で、「あしらい」とも表現されます。
大根のつまを刺身の下に敷くことで、立体的で豪華な見た目を作り出します。
大根を食べると、口の中がさっぱりし、魚の脂っこさを軽減してくれるため、後味が爽やかになります。
さらに、その特有の香りと食感は、刺身の味わいをさらに引き立てます。
刺身は本来水分を多く含んでおり、時間が経つにつれて鮮度が落ちることがありますが、大根のつまはこの余分な水分を吸収し、鮮度を保つのに一役買います。
また、大根に含まれる成分には、刺身の保存性を向上させる働きがあります。
過去には冷蔵技術が未発達だったため、これが特に重宝されました。
大根のつま、食べるかどうか?
大根のつまを食べることはマナー違反ではありませんし、多くのメリットがあります。
食べることは必須ではないですが、大根は体に良い成分を豊富に含んでいますので、試してみる価値は十分にあります。
刺身のつま、食べるべきか残すべきか
刺身に添えられるつまは、単なる装飾ではなく、食品の鮮度を保つなどの伝統的な役割を持っています。
つまを刺身と一緒に食べることで、これらのパワーを実感できます。
つまには大根の千切りだけでなく、大葉、穂じそ、小菊、海藻なども使われ、これらは見た目にも美しさを加えるだけでなく、刺身の味を引き立てます。
外食でつまを残すことが常に失礼にあたるわけではなく、食べることが下品とされることもありません。
食品を無駄にしないためにも、料理に工夫が感じられる場合は、つまも含めて楽しむことをおすすめします。
例えば、小菊の花びらを醤油に浸して食べることで香りを楽しんだり、穂じそを細かくして刺身と一緒に食べると、風味が増し、料理が一層美味しく感じられます。
余った刺し身のつまの再利用方法
家で刺し身を食べた後、つまが余ることがよくあります。
そのようなときは、余ったつまを味噌汁の具として使うのがおすすめです。
もし生臭さが気になる場合は、使用する前に水で軽く洗い流すといいでしょう。
刺身に添えられる「つま」の歴史とその意味

刺身に付け合わせが添えられるようになったのは江戸時代中期からです。
この付け合わせは「あしらい」とも呼ばれ、スタイルによって「けん」「つま」「からみ」の三つに分けられます。
「けん」は大根、ニンジン、キュウリなどを細長く切って刺身の後ろに高く盛り付けるスタイルです。
「つま」は刺身の横や前に配置される少量の野菜や海藻、大葉などで、視覚的に華やかさを加える役割を担います。
「からみ」はワサビやおろしショウガなど、辛味を添える要素で、味のアクセントとして用いられます。
刺身の大根のつまを食べる?残す?そのマナーについて【まとめ】

刺身と共に提供される大根の千切り「つま」について、その利用とマナー、歴史的背景などを検討しました。
つまの食べるかどうかは個人の選択であり、マナー違反ではありません。
魚の脂の重さを軽減し、刺身の風味を引き立てる力があるため、積極的に食べることが推奨されます。
また、外食でつまを残すことが必ずしも失礼とは限らないものの、食品ロスを避け、料理を全体として楽しむためにも食べることが望ましいとされています。
つまは装飾的な要素だけでなく、刺身の鮮度保持や見た目の美しさを向上させる役割も担っています。
江戸時代中期に始まったこの伝統は、大根、ニンジン、キュウリを使った「けん」、香りや彩りを添える「つま」、辛味を加える「からみ」に分類されます。
食べ残したつまは味噌汁の具として再利用することもでき、無駄を減らし新たな味わいを楽しむ一助となります。
このように、つまは刺身をより一層楽しむための重要な要素であり、その多様な利用法を知ることは日本料理の深い理解に繋がります。
食べるのがおすすめではありますが、そうでない場合もあります。
刺身のつまが赤く変色している場合や長時間放置されている場合は、食べる必要はありません。
これらの状態は食材の品質が落ちている可能性を示しているからです。
しかし、つまが新鮮な状態で提供されていれば、刺身とともに食べることで、その美味しさを存分に楽しむことができます。
次回、刺身を食べる時にこの記事の内容を思い出して、参考にしてみてください。
ありがとうございました。