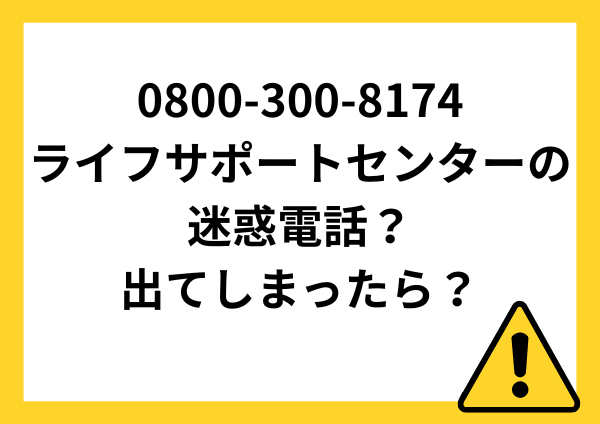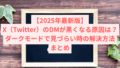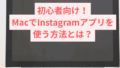突然「0800-300-8174」から電話がかかってくると、
- 詐欺?危険?
- 出てしまったら?
- どこの会社?
こんなふうに一瞬で不安になりますよね。
結論からお伝えすると、
0800-300-8174は「ライフサポートセンター」名義で発信される、電気・ガス・通信料金の“切り替え営業”の電話です。詐欺ではありませんが、しつこい勧誘が多く、出る必要はありません。
この記事では、より詳しく安心していただけるよう、
- 正体の詳細・背景
- 実際にユーザーが受けた勧誘内容の具体例
- どんな危険性があるのか
- 無視していい理由
- 確実な撃退法(スマホ別)
- 同じ仕組みでかかってくる別番号の一覧
- なぜこのような電話が増えているのか(背景)
まで、徹底的に網羅しました。
不安が強い方でも、この記事を読み終えるころには“対処が明確”になり安心できます。
0800-300-8174はどこ?正体と運営の背景を徹底解説

ライフサポートセンター名義で発信される営業電話
口コミを調べると、多くの人が次のように名乗られたと報告しています。
- 「ライフサポートセンターです」
- 「電気料金の見直し窓口です」
- 「お客様の料金が安くなるご案内です」
- 「電気とガスの契約をまとめると安くなるのでお知らせしています」
いずれも公式の契約会社ではなく、第三者の営業代行会社です。
電気・ガス・通信の切り替えを勧めるのが目的
近年急増している“乗り換え営業”で、
- 電気会社の乗り換え
- ガス会社の変更
- 光回線の見直し
- セット割の案内
が主な内容です。
“安くなる”と言われると魅力的に感じますが、後で契約内容を確認すると割高になるケースもあり、トラブルも少なくありません。
どこから番号が流れているの?
0800-300-8174に限らず、こうした営業電話の番号は次のような経路から得られます。
- 過去に光回線・電気の比較サイトで入力した番号
- 資料請求やキャンペーン応募
- マンション設備の回線契約情報
- 名簿業者からの購入
自分の個人情報がどこで取得されたのかは特定できませんが、“公式の番号ではない”点だけは確実です。
この電話は危険?詐欺ではないが注意が必要な理由

0800-300-8174は詐欺ではありませんが、注意したい理由があります。
丁寧な営業に見せかけて契約を急かされる
口コミでは、
- 「安くなるので今すぐ切り替えましょう」と急がされた
- 詳しい説明がないまま契約を迫られた
- 他社より安いと強調され続けた
などの声が多く、判断力が鈍った状態で契約してしまう人もいます。
個人情報を聞かれるケースが多い
次のような情報を聞かれたという口コミが多数あります。
- 電気・ガスの契約番号
- 検針票の内容
- 現在の契約会社
- 家族構成
公式カスタマーサポート以外に個人情報を話すのは危険です。
「無料点検」を装うケースもある
少数ですが、「近くに行くので点検します」という提案から訪問につなげられそうになった例もあります。
しつこい繰り返しの着信
無視しても、
- 時間帯をずらして何度も着信
- 留守電にメッセージ
などが続くケースがあります。
電話に出てしまったらどうする?

「つい出てしまった…」と気づいた瞬間、ドキッとしますよね。
でも大丈夫です。出てしまったからといって、すぐに被害が出るわけではありません。
落ち着いて、以下のポイントを確認してください。
個人情報は絶対に話さない
相手がどんなに丁寧な口調でも、次の情報は一切伝えないようにしましょう。
-
名前(フルネーム)
-
住所や最寄り駅
-
生年月日
-
クレジットカード番号
-
家族構成や在宅時間
「確認のためです」「すでに登録されています」と言われても、
こちらから答える必要はありません。
すぐに電話を切ってOK
違和感を覚えたら、
「結構です」「必要ありません」と一言伝えて、すぐに切って大丈夫です。
相手に気を遣う必要はありませんし、
無言で切ってもマナー違反にはなりません。
折り返し電話はしない
着信履歴を見て気になっても、
自分から折り返すのは避けましょう。
折り返すことで、
-
「つながる番号」と認識される
-
さらに別の番号からかかってくる
といった可能性が高くなります。
不安な場合は着信拒否を設定する
一度出てしまって不安になった場合は、
早めに着信拒否設定をしておくと安心です。
スマホの標準機能だけで簡単に設定できますし、
同じ番号からの再着信を防げます。
被害が心配なときは相談窓口へ
もし「個人情報を話してしまったかも…」と不安な場合は、
早めに相談することで被害を防げます。
-
消費生活センター(局番なし:188)
-
携帯キャリアのサポート窓口
「大したことじゃないかも」と思っても、
相談するだけでも安心につながります。
実際に受けた人の口コミまとめ(匿名化した内容)

ネット上の口コミには、次のような傾向が見られます。
急に契約内容を説明され不安になった
「料金が安くなると言われたが、何がどう安くなるのか説明が曖昧で怖くなった」
断っても何度もかかってきた
「忙しい時間に3回着信。番号を調べてすぐ着拒した」
親切だったという人も
「営業の割には丁寧に説明してくれた。ただ結局契約はしなかった」という少数意見もありました。
“あたかも公式”のような話し方
「『契約変更が必要です』と公式のような言い方で焦った」という声もあり注意が必要です。
【重要】出てもいい?無視して大丈夫?折り返しは必要?

出る必要なし → むしろ出ないほうが安全
0800〜の番号は営業電話で使われることが多いため、出る必要はありません。
折り返し電話は絶対に不要
- 情報が“つながる番号”として登録される
- 別の営業会社にも情報が流れる可能性
があるため、折り返しは避けましょう。
無視・着拒で何の問題もない
公式窓口からの連絡ではないため、無視してOKです。
【撃退法】二度とかかってこないための確実な対処法

ここでは、スマホ別の撃退方法を詳しく解説します。
iPhoneの場合
- 着信履歴を開く
- 「i」マークをタップ
- 「この発信者を着信拒否」を選ぶ
Androidの場合
- 電話アプリを開く
- 該当番号を長押し
- 「ブロック」または「迷惑電話に設定」を選択
携帯会社の迷惑電話ブロックを利用
- docomo:あんしんセキュリティ
- au:迷惑メッセージ・電話ブロック
- SoftBank:迷惑電話ブロック
これらをオンにしておくと、自動で検知してくれます。
LINE/Yahooの迷惑電話警告機能
番号に色付き警告が表示されるため、安心して判断できます。
似た番号に注意!同じ仕組みでかかってくる他の営業番号

0800・050・0120の番号は、営業で使われることが多いです。よく報告される例:
- 0800-111-XXXX(光回線)
- 0120-XXX-XXX(電気会社乗り換え)
- 050-XXXX(ネット関連の営業)
このような番号からの着信は、まず調べてから判断するのが安全です。
なぜ営業電話がこんなに増えているの?

背景を知ると、落ち着いて対応できるようになります。
電力自由化で“代理店営業”が急増
2016年の電力自由化以降、競争が激しくなり、多くの会社が外部の営業代行に委託しています。
ガス・光回線・電気を「セット販売」したい会社が多い
セット割を勧めるため、電話営業を強化している企業が増えています。
個人情報の流通経路が複雑化
ネットで一度でも入力した情報が、複数の会社に回る時代です。
まとめ|0800-300-8174は“出なくてOKの営業電話”

最後に改めて要点をまとめます。
- 0800-300-8174はライフサポートセンター名義の営業電話
- 詐欺ではないが、説明不足や強引な営業例がある
- 個人情報を伝えるのは危険
- 出る必要なし、折り返しは絶対しない
- しつこい場合は着信拒否でOK
- 迷惑電話対策をしておけば安心
少しでも不安が解消され、安心して対策できることを願っています。