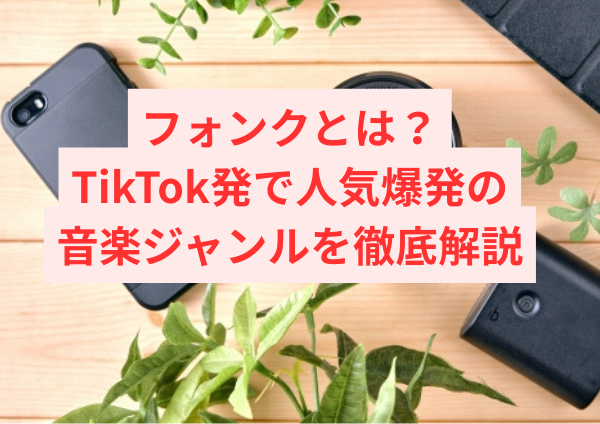フォンクとは?TikTokで人気が高まる新ジャンル

フォンクの読み方・意味・定義
フォンクは「Phonk(フォンク)」と読み、90年代アメリカ南部のヒップホップ文化を土台に進化した音楽ジャンルです。名前の由来には諸説ありますが、「Funk(ファンク)」と似た語感をもちつつ、もっと暗くて不穏で、無機質な雰囲気をまとった新しいスタイルとして広がりました。TikTokで広まった現在は、初心者でも聴きやすく、どこかクセになる“エモさ”や“夜の空気感”が魅力と言われています。
メンフィス・ラップとの関係とルーツ
フォンクのルーツは、1990年代のメンフィス・ラップに深く結びついています。当時のアンダーグラウンドな作品には、荒削りでローファイ、重低音が強めのサウンドが多く、その質感が現代フォンクにも強く受け継がれています。特に、Three 6 Mafiaなどのアーティストが残した文化は大きな影響を与えており、現代のフォンクは“メンフィスの魂を現代風に蘇らせた音楽”として注目されています。
いつから流行し始めた?拡大していった背景
フォンクがSNSで急激に広がったのは2020年前後です。海外ではYouTubeの自動生成ミックスから人気が高まり、日本ではTikTokの車・夜景・ドリフト系編集動画で一気に認知が拡大しました。無機質で中毒性が高い音が、ショート動画のテンポと相性抜群だったこともあり、Z世代を中心に「この音なに?」「カッコいい!」と拡散。さらに、編集映えすることからクリエイターが積極的に採用したことで、爆発的に広がっていきました。
フォンクの世界観と魅力をざっくり紹介
フォンクの世界観は、“夜”“スピード感”“都会の無機質さ”“アンダーグラウンド感”といったキーワードで語られることが多いです。音自体はシンプルでありながら、独特の浮遊感やミステリアスな空気をまとっており、聴く人の想像をかき立てる力があります。集中したいときのBGMにもよく使われ、日常の中にひそかな刺激やワクワク感を与えてくれる、そんな魅力を持っています。
フォンクの音楽的特徴とは?

体に響く重低音と独特のリズム
フォンクの大きな特徴のひとつが、体の奥まで届くような重低音です。イヤホンやスピーカーで聴くと、ズンと響くベースが心臓のリズムと重なるような感覚になり、思わずリズムにのってしまうほど。テンポは比較的ゆったりしているのに、どこか引き込まれる心地よさがあり、「作業中にずっと聴いてしまう」という人も多いです。独特のリズム構成もクセになりやすく、ループされるようなビートが集中力を保ちつつ気分を切り替えてくれる魅力があります。
クセになる“カウベル”のサウンド
フォンクといえば外せないのが“カウベル”と呼ばれる独特の金属的な音。チーンという軽い響きながらも、リズムの中でアクセントとして強く印象に残ります。無機質なビートの中でこのカウベルが入ることで、音に抜け感やキレが生まれ、聴き手に爽快さを与えるのが特徴です。シンプルなフレーズでも耳が自然と反応してしまうほど中毒性があり、「あ、これフォンクだ」と一瞬でわかる音のひとつになっています。
90年代ヒップホップのサンプリング文化
フォンクの魅力を語るうえで欠かせないのが“サンプリング”。古いカセットテープのようなザラついた声や、ヴィンテージ感のあるドラム音など、90年代ヒップホップの素材を現代風に加工して使うのが定番です。あえてノイズ感を残したり、音程を下げて不穏さを出したりすることで、フォンク独特の“退廃的でダークな雰囲気”が完成します。過去の音と現代のビートがミックスされたその世界観は、音楽好きの間でも「懐かしいのに新しい」と高く評価されています。
スクリュー(Pitch Down)で作る不穏な雰囲気
スクリューとは、音程を大きく下げて低くゆっくりした質感を生み出す加工のことです。フォンクではこのスクリューが非常に重要な役割を持っていて、もともとの音源に“影”を落とすような、どこか不安を感じる空気をつくり出します。声のピッチを下げると、一気にダークで神秘的な雰囲気がまとまり、聴く人の心をじわっと掴む独特のインパクトが生まれます。まるで暗い夜道を一人で歩いているような静けさや、不穏なムードを演出できるため、TikTokの夜景・車・都市系の動画とも非常に相性が良いとされています。
さらに、スクリュー加工は“音の余白”を増やす効果もあるため、通常のビートに比べてゆったりとした空間が感じられます。その分、他の音が際立ちやすくなり、重低音やカウベルなどフォンクの特徴的サウンドがより印象的に響くようになります。初めてフォンクを聴く方でも、このスクリューによるミステリアスな雰囲気はついクセになってしまう要素のひとつです。
808ベースやノイズの使い方
808ベースは、フォンクの迫力を支える“土台”ともいえる重要な音です。太く深い低音が特徴で、聴く人の身体に直接響くようなパワーを感じさせます。特にフォンクでは、808ベースをあえて歪ませたり、音をざらつかせたりすることで、アンダーグラウンド感をより強く演出しています。まるでスモークの中にいるような、重たく沈み込むような雰囲気をつくり出せるのが魅力です。
また、フォンクでは“ノイズ”をあえて入れることも多く、古いカセットテープのような質感やレコード特有のパチパチ音が混ざることで、音全体にビンテージ感が加わります。クリアで整った音とは真逆の、粗くて生々しい質感を大切にするのがフォンクらしさともいえます。この独特のノイズが、どこか懐かしく、そして不思議と落ち着く雰囲気を演出し、フォンクならではの世界観をより深く作り上げています。
フォンクがTikTokで人気を集める理由

短尺動画と相性が抜群な音の展開
フォンクは、短い時間の中でも“雰囲気を一瞬で伝えられる”という大きな強みがあります。イントロからいきなり世界観が立ち上がるため、数秒で勝負するTikTokのような短尺動画とは驚くほど相性が良いんです。最初の2〜3秒だけで視聴者の耳をつかみ、スクロールを止めてもらえるので、クリエイターにとっては信頼できる“掴みの音楽”として選ばれやすくなっています。また、ループさせても違和感がないリズム構成のため、動画の長さに合わせやすいのも人気の理由のひとつです。
ハッシュタグ文化とアルゴリズムバズ
TikTokはハッシュタグの使い方ひとつで再生数が大きく変わる仕組みになっており、フォンク界隈でも「#phonk」「#driftphonk」などのタグが定番化しています。こうしたタグをつけることでアルゴリズムに乗りやすくなり、フォンクを使った動画は関連動画に入りやすくなる傾向が強まります。結果としてフォンクは動画投稿者同士で自然と広がる“コミュニティ的拡散”が起こりやすく、ひとつのタグから新しいトレンドが生まれることも珍しくありません。タグを追うだけで新しい曲に出会えるため、視聴者にとっても便利な仕組みとなっています。
映像編集とフォンクの相乗効果
フォンクの無機質で重厚な雰囲気は、映像編集との相性がとても良いのが特徴です。特に、車のドリフト映像や夜景、街のタイムラプス、ネオンが光るシーンなどはフォンクの音と組み合わせるだけで一気に“映画のワンシーン”のようなクオリティに仕上がります。動画クリエイターから見ると、フォンクは“置くだけで映像が締まる音楽”として扱いやすく、初心者でも手軽にスタイリッシュな動画を作りやすいという魅力があります。また、音の抜き差しやビートの強弱に合わせて映像をカットすると、視覚と聴覚がリンクしてさらに没入感が増し、観る人への印象を強く残せるようになります。
TikTokでよく使われるフォンクの演出パターン
TikTokでは、フォンクが使われる動画にはいくつか定番の演出パターンがあります。代表的なのは、車の走行シーンやドリフト映像に合わせてリズムを切る編集。ほかにも夜景をスローモーションで見せたり、都会の風景をモノクロやネオンカラーで強調したりと、少し“非日常感”を演出する動画が人気です。また、日常のルーティン動画にフォンクを合わせて、あえてギャップを出す演出も増えてきています。シンプルな映像でも雰囲気が一気におしゃれになるため、初心者クリエイターでも使いやすい音楽として広く受け入れられています。
フォンクのサブジャンルをわかりやすく解説

ドリルフォンクとは?
ドリルフォンクは、フォンクの中でも特に“攻撃的でスピード感のある”サブジャンルとして知られています。重低音が強めで、ビートが鋭く刻まれるのが特徴。まるで疾走感のある映像を見ているようなリズムが続くため、TikTokやYouTubeのドリフト映像との相性がとても良いとされています。さらに、ドリルフォンクはメロディよりもビートで魅せるタイプの音楽なので、聴いているだけで気分がグッと引き締まり、集中力が高まるという声も多いです。初心者でも比較的入りやすく、フォンクの躍動感を味わいたい方にぴったりのスタイルです。
トラップフォンクとは?
トラップフォンクは、名前の通り“トラップミュージック”の要素を強く取り入れたフォンクのサブジャンルです。特徴としては、808ベースの強烈な振動や、ハイハットの細かい刻み、どこか感情を抑えたようなクールな雰囲気があります。フォンク特有の退廃感に、トラップのスタイリッシュさが加わることで、都会的で洗練された印象に仕上がります。夜の街を歩くようなゆったりとした気分で聴けるため、作業BGMとしても人気が高いジャンルです。落ち着いたトーンなのに存在感があり、リピートしたくなる独特の魅力があります。
メンフィスリバイバルとは?
メンフィスリバイバルは、フォンクの原点となる“メンフィス・ラップ”をより強く反映したサブジャンルです。90年代のローファイで荒削りな音質や、深いリバーブ、ダークなサンプリングなど、古き良きメンフィス文化を現代風に甦らせたスタイルが特徴。昔のカセットテープを思わせるザラついた質感や、あえてノイズ感を残したサウンドが多く、ノスタルジックさとアンダーグラウンド感が同時に楽しめます。“原点回帰”ともいえるこのスタイルは、フォンク上級者や、本格的な雰囲気を好むリスナーに特に人気があります。
トラップフォンクとは?
トラップフォンクは、トラップミュージックの鋭いハイハットや重低音をベースにしながら、フォンク特有のダークさやローファイ感をほどよく融合させたスタイルです。よりモダンで洗練された印象があり、都会的な雰囲気のある動画やスタイリッシュな編集に合わせやすいのが魅力です。深夜の街を歩いているような静かな高揚感が続き、作業中のBGMとしても人気が高まっています。初心者でも取り入れやすい安定したビート感があり、「フォンクを初めて聴くならまずここから」という人も少なくありません。
メンフィスリバイバルとは?
メンフィスリバイバルは、90年代メンフィス・ラップをそのまま現代に蘇らせたような、原点回帰型のフォンクスタイルです。ザラついた質感、雑音混じりのボーカル、低いピッチ加工など、あえて“荒削りなまま”の音を残しているのが特徴。聴けば聴くほどクセになる独特の空気感があり、古いカセットテープを思わせる音の濁りが、より一層アンダーグラウンドな雰囲気を演出してくれます。フォンクのルーツをじっくり感じたい方におすすめのジャンルです。
それぞれの違いと聴き分けポイント
トラップフォンクは「モダンでクール、都会的」な印象が強く、リズムがはっきりしていて聴きやすいのがポイント。一方、メンフィスリバイバルは「ローファイで粗削り、退廃的」なムードが前面に出ているため、より深い世界観が味わえます。ドリルフォンクと比べるとスピード感は控えめですが、その分ひとつひとつの音がしっかり響き、じっくり聴くほど味が出るのが特徴です。気分によって聴き分けるのもおすすめで、集中したいときはトラップフォンク、世界観に浸りたい時はメンフィスリバイバルを選ぶと心地よく楽しめます。
代表アーティストの紹介
トラップフォンクなら Kordhell や Dxrk といったアーティストが世界的に人気で、TikTokでも頻繁に使われています。スタイリッシュなビートが魅力で、どの曲も映像と合わせやすいのが特徴です。メンフィスリバイバルでは DJ Smokey や Pharmacist が代表格で、深いローファイ感とミステリアスな世界観が高く評価されています。それぞれのアーティストごとに雰囲気が異なるため、好みの音を探しながら聴き比べてみるとよりフォンクの奥深さを味わえます。
日本でフォンクが広まった背景

YouTube車系動画・ショート動画の影響
YouTubeでは、車系チャンネルやドリフト映像を中心にフォンクの使用が一気に広まりました。エンジン音やタイヤのスキール音とフォンクの重低音が心地よくミックスされることで、視覚と聴覚の両方に訴える“没入感のある映像”が完成します。またショート動画文化の浸透により、テンポの良いフォンクは動画クリエイターにとって非常に扱いやすい音源に。特に車のローアングル映像や夜の高速道路、都会の光を背景にしたシーンでは、たった数秒で視聴者の心を掴めるとして幅広く使われるようになりました。
TikTok国内クリエイターの発信力
TikTokの国内クリエイターたちは、フォンクを自分らしい表現方法として取り入れ、次々と新しいトレンドを生み出しています。日常のルーティン動画にフォンクを合わせて“おしゃれな雰囲気”を出したり、夜の街歩き動画に使ってムードを底上げしたりと、使い方はとても自由。音楽の解説系クリエイターや車系インフルエンサーも積極的にフォンクを紹介し、視聴者が自然と新しい曲に出会える仕組みができあがりました。クリエイター同士のコラボやリミックス投稿も多く、フォンク人気の広がりに大きく貢献しています。
Z世代に刺さる“無機質×疾走感”の世界観
Z世代がフォンクに魅了される理由のひとつが、その“無機質なのに疾走感がある”不思議な世界観です。TikTokやショート動画では、素早く世界観を伝えられる音が求められますが、フォンクはその条件にぴったり。重低音とカウベルの抜ける音が混ざり合い、わずか数秒で映像の雰囲気を一気にドラマチックにしてくれます。また、どこか感情を抑えたような冷静さと、心がざわつくようなスピード感が共存しており、Z世代の“静かな刺激を求める感性”に絶妙にフィットしているといえます。
海外トレンドを吸収する日本カルチャーとの相性
日本のカルチャーは、海外のトレンドを柔軟に吸収し、自分たちの生活に合わせてアレンジしていくのがとても得意です。フォンクもその一例で、車文化・映像編集・ファッションなど幅広いジャンルと自然に融合しながら広がっていきました。特に日本では、都会の夜景やストリートスタイルとの相性が抜群で、フォンクを使うだけで“世界観が完成する”と感じるクリエイターが多いようです。また、アニメやゲーム系の編集とも相性が良く、日本独自の使われ方が進化しているのも特徴です。
フォンクと車・ストリートカルチャーの関係

ドリフト映像との組み合わせが支持される理由
フォンクがドリフト映像とこれほどまでに相性が良い理由は、音と映像の“スピード感の一致”にあります。フォンク特有の重低音と鋭いビートは、車がカーブを切る瞬間やタイヤが滑る軌跡とぴったり重なり、視覚と聴覚の両方に刺激を与えてくれます。また、無機質でクールな世界観が、車の金属光沢や夜の道路の反射と見事に溶け合い、たった数秒の動画でも迫力あるシーンに仕上がります。編集初心者でも“置くだけで映える”ため、車系クリエイターがこぞってフォンクを使い始めたのも納得です。
アンダーグラウンド精神とのつながり
フォンクのルーツには、アンダーグラウンドな文化が深く根付いています。暗く荒削りな音質、ノイズの混ざったローファイ感、反体制的で独立志向のエネルギー——これらはメンフィス・ラップの時代から脈々と受け継がれてきた要素です。ドリフトやストリートカルチャーにも、既存の枠にとらわれず“自分らしさを貫く”精神があり、フォンクの持つ世界観と自然にリンクします。洗練されすぎない、どこか粗さの残る感じが逆に魅力となり、若い世代から強く支持されているのです。
世界での派生スタイル
フォンクは世界中で進化し続けており、国や地域によって個性豊かな派生スタイルが生まれています。例えばヨーロッパでは、電子音を強く取り入れたクリーンな“ユーロフォンク”が人気。一方、中南米では情熱的なビートとローカル音楽を融合させた“ラテンフォンク”が注目されています。さらに、アジア圏ではK-POPのダンス映像やゲーム編集との組み合わせが広まりつつあり、フォンクはグローバルなカルチャーとして新たなステージへと進化しています。この広がりが、フォンクというジャンルの懐の深さと柔軟性を物語っています。
日本ではどう浸透している?
日本では、まず車・バイク系の映像を中心にフォンクが人気となり、次第に日常系・Vlog系・ファッション系へと広がっていきました。都会の夜景やネオンカラーの街並みとの相性が良いため、フォンクを使うだけで動画全体が“おしゃれで没入感のある雰囲気”になると感じるクリエイターも多いです。また、アニメ系編集との親和性も高く、AMV(アニメミュージックビデオ)でも頻繁に使用されるようになりました。最近では、Z世代のアーティストがフォンク風の楽曲を自主制作するなど、音楽ジャンルとしての広がりも見せています。
フォンクはどう作られている?音の作り方の秘密

サンプリング
フォンクに欠かせない技法で、過去の音源や声素材を切り取って新しい曲に取り入れる方法のことです。特に90年代のメンフィス・ラップや古いカセットテープのようなザラついた素材がよく使われ、フォンク特有の“退廃的でダークな空気感”を作り出します。あえてノイズや劣化した質感を残すことで、懐かしさと新しさが同時に感じられるのが大きな魅力です。現代的なクリアさとは違う“ビンテージ感”がリスナーの心を掴み、フォンクの世界観を深めています。
カウベル
フォンクの象徴ともいえる金属的で乾いた“チーン”という音。ビートの中でアクセントとして鳴らされ、曲全体に抜け感やキレの良さを与えてくれます。とてもシンプルな音なのに一度聴くとクセになる中毒性があり、「あ、これはフォンクだ」と一瞬でわかるほど特徴的。夜のドライブ映像や都会の夜景と合わせると、映像の雰囲気を一気にスタイリッシュに変えてくれる魔法の音色です。
スクリュー
音程を下げて低くゆっくりした質感を作る加工のこと。声やサンプル素材をスクリューさせることで、深夜の都会を思わせるようなダークでミステリアスな雰囲気が生まれます。フォンクの“影”“静けさ”“不穏さ”を象徴するような表現で、世界観に奥行きを与えてくれる存在です。やりすぎない程度にピッチを下げるのがポイントで、音の余白が増え、重低音やカウベルの存在感がより際立ちます。
808ベース
フォンクの土台を支える、とても重要な低音の要素。身体に響くような太く深い低音が特徴で、曲全体の迫力をつくり出します。フォンクでは808をあえて歪ませたり、ざらついた質感に加工したりすることで、よりアンダーグラウンドな雰囲気を強調することが多いです。夜道を走る車のような重さや、不穏で芯のある存在感がフォンクの魅力を一段と深いものにします。
メンフィスリバイバル
90年代メンフィス・ラップを現代に蘇らせたようなフォンクのスタイル。ノイズ混じりのボーカル、ローファイで荒削りな音質、低いピッチ加工など、“昔のカセットテープ”を思わせるようなサウンドが特徴です。原点回帰ともいえるジャンルで、フォンクのルーツをしっかり味わいたい人に特に人気があります。どこか懐かしく、でも深く刺さる唯一無二の世界観が感じられるカテゴリーです。
まとめ|なぜフォンクは若者を魅了するのか?
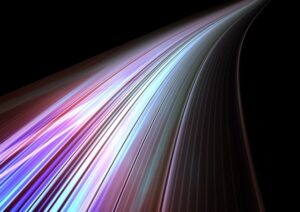
フォンクの魅力をおさらい
フォンクは、重低音の迫力・ローファイな質感・どこか退廃的でミステリアスな雰囲気など、ほかのジャンルにはない独特の魅力をもっています。夜景や車、都会の風景と相性がよく、映像と組み合わせることで一気に世界観が深まる点も人気の理由です。さらに、作業中に流してもリズムが邪魔にならず、むしろ集中力を高めてくれるという声も多いです。初心者にとって“聴きやすさ”と“スタイリッシュさ”のバランスがちょうどよく、気軽に楽しめるのもフォンクの大きな強みといえます。
ライフスタイルに溶け込む新しいBGM
フォンクは、ただ聴くだけで気分を切り替えられる“新しいタイプのBGM”としても注目されています。朝の準備や夜のリラックスタイムに流せば、一日の気分が自然と落ち着いたり、逆にシャキッとしたりと、シーンに合わせて心を整えてくれる存在に。散歩や通勤時間に聴くと、いつもの景色が少し特別に見えたり、まるで映画のワンシーンに入り込んだような感覚が味わえることもあります。自分のペースや気持ちに合わせて聴けるのが、フォンクが “生活に寄り添う音楽” として人気を集めている理由です。
これからフォンクを楽しむために
フォンクをさらに楽しむためには、まずはお気に入りのアーティストやミックスを見つけるところから始めるのがおすすめです。Spotify や YouTube には初心者向けのプレイリストが多く、聴き比べるだけでも自分の好きな“フォンクの傾向”が自然とわかってきます。また、気に入った曲を日常のBGMとして取り入れることで、フォンクの世界観をもっと身近に楽しめるようになります。作業中、運動中、夜のリラックスタイムなど、さまざまな場面で流してみて、自分のライフスタイルに合うシーンを探してみてください。“フォンクがある日常”はきっと今より少しだけ心地よく、刺激的になります。