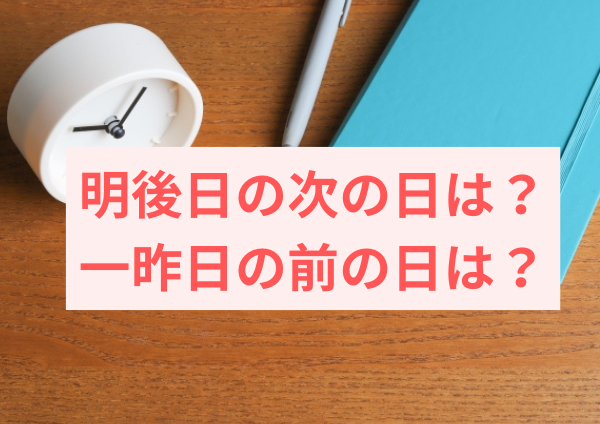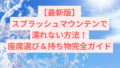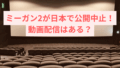明日・明後日・昨日・一昨日とは?|まずは基本の呼び方を確認

明日(あした/あす)とは?
明日とは「今日の次の日」のことを指します。日常会話やビジネスでもよく使われる表現ですね。カレンダー上では「翌日」とも言い換えられ、予定やスケジュール調整の場面でも頻出します。「明日は雨が降るらしいよ」「明日までに提出してね」といったように、非常に多用される時制表現です。
明後日(あさって)とは?
明後日は「今日の次の次の日」、つまり2日後のこと。明日ではなく、その次の日です。たとえば今日が月曜日なら、明後日は水曜日になります。会話の中では、「あさって出かけよう」「あさってまでに終わらせるよ」などと自然に使われ、家族とのやりとりや予定調整の中でよく登場します。なお、「あさって」は漢字で「明後日」と書くのが一般的です。
昨日(きのう)とは?
昨日は「今日の前の日」、つまり1日前のこと。最も基本的な過去の表現です。日常生活では「昨日何食べた?」や「昨日のドラマ見た?」など、振り返りの場面で多く使われます。日本語では「昨日」を「さくじつ」と読むこともありますが、これは主に書き言葉やニュース、ビジネス文書で使われる表現です。
一昨日(おととい)とは?
一昨日は「今日から数えて2日前」のこと。昨日のさらに前の日ですね。たとえば今日が木曜日であれば、一昨日は火曜日になります。「おとといから体調が悪い」「おとといの会議で話題に出た」など、過去の出来事を少し前にさかのぼって伝えるときに便利な言葉です。漢字では「一昨日」と書き、「いっさくじつ」と読むこともありますが、これも書き言葉での使用が中心です。
「明後日」の次の日は?さらにその先もわかりやすく紹介

明々後日(しあさって)とは?
明後日の次の日は「明々後日(しあさって)」と呼ばれます。つまり今日から数えて3日後のことになります。たとえば今日が月曜日なら、明々後日は木曜日になります。この言葉は日常会話でも時折使われ、「明々後日に会議があるよ」「旅行は明々後日からだよ」など、スケジュール調整などで重宝されます。ただし、日によっては「3日後」という具体的な表現のほうが伝わりやすいため、TPOに応じた使い分けが大切です。
その次は「やのあさって」?「ししあさって」?
さらにその次、4日後を「やのあさって」や「ししあさって」と呼ぶ地域もあります。これは主に関西圏を中心とした方言的な表現で、標準語としてはあまり使われていません。たとえば、「やのあさってに実家へ帰る予定」などのように、関西出身の人が口語で使うことがあります。ただし、初めて耳にする人にとっては意味が分かりにくいので、状況に応じて補足説明を加えると親切です。
地方によっても違う?呼び方のバリエーション
地域によっては「ししあさって」「ごあさって」「ややのあさって」など、さらに独特な表現を使うこともあります。これらの表現は世代や地域によって使われる頻度に差があり、現代ではあまり耳にしなくなっているケースもあります。
中には、「ししあさって」が4日後を指すと認識している人と、5日後だと思っている人が混在していることもあり、混乱の原因になることも。特に複数人で予定を立てる場面では、誤解を防ぐためにも「○月○日」や「○日後」といった具体的な日付で共有するのがベストです。
「一昨日」の前の日は?さらにさかのぼると?

二昨日(さきおととい)とは?
一昨日の前の日は「さきおととい(二昨日)」と呼ばれます。今日から3日前という意味です。たとえば、今日が金曜日なら、二昨日は火曜日になります。会話の中ではあまり頻繁には登場しない表現ですが、「さきおとといは出かけてたよ」や「さきおとといからずっと雨だね」といったように、文脈によって自然に使われることもあります。「さきおととい」は、「先一昨日(せんおととい)」と表記される場合もあり、地域や世代によって使い方にばらつきがあります。
その前の日は何という?
今日から4日前になると、「やのおととい」「ししおととい」などの表現が一部の地域で使われています。これらは関西地方や一部の西日本エリアで耳にすることがあり、日常会話というよりは昔ながらの言い回しとして親しまれていることが多いです。
また、「ややのおととい」「ごおととい」など、さらにバリエーションがある地域も存在します。ただし、どれも標準語としては定着しておらず、あくまで方言的な存在であることに注意が必要です。これらの表現を使う際は、相手との共通理解があるかを確認すると安心です。
古語や方言にある独自の呼び方も
古語や方言では、さらに独自の言い回しがあることもあります。たとえば、「いっさくさくじつ」「さくさくじつ」など、書き言葉や古典文学の中に登場するような語彙も見られます。
また、明治・大正時代の文献の中では、日数を表すのに「○日以前」といった形式で表現されることも多く、現在のような口語表現は少なかったとされています。
言葉の変遷をたどることで、日付の呼び方がどのように進化してきたのかを感じ取ることができ、言語としての日本語の豊かさが見えてきます。
呼び方の由来と歴史を知ろう

「明日」「明後日」はいつから使われていた?
これらの言葉は古くから使われており、日本語の中でも基本的な時間の概念として定着しています。「明日(あす)」や「明後日(あさって)」は、平安時代の文献にもすでに登場しており、当時から日常的に使われていたと考えられています。
古典文学や和歌の中では、情緒を表現する際にこれらの言葉がしばしば用いられており、時間の流れを感じさせる役割を果たしていました。また、仏教用語の中にも時間を表す語句が多く存在し、それらの影響で一般に浸透したとも言われています。
江戸時代以降は庶民の間でも広く使われ、日常会話の中で「明日来てください」「あさっては休みです」など、現在とほとんど変わらない形で使われていた記録が残っています。
古語や方言が今に残る例
地方での独特な表現には、古語が起源となっているものも多くあります。たとえば、「さくじつ(昨日)」や「いっさくじつ(一昨日)」などは、もともと文語的な表現でしたが、今でも公式な文書や報道などでは見かけることがあります。
また、地方によっては「さくいち」「いっさく」など、より簡略化された表現が口語として残っている場合もあります。これらの古語や方言は、地域の文化や言語感覚を色濃く反映しており、日本語の多様性を示す一例とも言えるでしょう。
学校教育ではあまり触れられない部分ですが、地域のお年寄りの話などに耳を傾けることで、こうした言葉の魅力を再発見できるかもしれません。
日付の呼び方一覧|スッキリ早見表

未来の日付(今日から見て)
- 今日:現在の日。すべての基準となる日です。
- 明日(1日後):今日の翌日。もっとも一般的な未来の表現。
- 明後日(2日後):明日の次の日。2日先の予定に使います。
- 明々後日(3日後):明後日の次の日。旅行やイベントでよく出てくる表現。
- やのあさって/ししあさって(4日後):方言で使われることの多い表現。4日後を意味します。
- ごあさって/ややのあさって(5日後):さらにその先の未来を表す地域限定の言い方。
- そのまた明後日(6日後):あまり使われませんが、表現として存在します。
過去の日付(今日から見て)
- 今日:基準日。現在進行中の日です。
- 昨日(1日前):1日前の出来事を振り返るときに使われます。
- 一昨日(2日前):昨日の前日。2日前のことを指します。
- さきおととい(二昨日/3日前):一昨日のさらに前の日。少し昔の話に使われます。
- やのおととい(4日前):一部の方言で使われる、4日前を指す言葉です。
- ごおととい(5日前):「ごあさって」の反対語的な存在。地方によって使われることがあります。
- そのまたおととい(6日前):さらに古い日付を指すこともありますが、日常的にはあまり登場しません。
よくある勘違い・間違いやすい表現まとめ

「明明後日」は間違い?正しいのは?
「明明後日」という表現は一般的ではなく、「明々後日(しあさって)」が正解です。
「明々後日」は、明後日の次の日、つまり今日から3日後を指す標準的な日本語表現です。一方、「明明後日」は漢字表記としては成り立つようにも見えますが、実際には国語辞典にもほとんど掲載されておらず、誤用とされることが多いです。
会話の中で聞き慣れない言い方が登場すると、相手を混乱させてしまう可能性もあるため、注意が必要です。また、「しあさって」や「みょうみょうごにち」など、ユニークな呼び方に引っ張られて「明明後日」と書いてしまうケースもあるので、文章を書く際にも気をつけましょう。
「おとといの次の日」は昨日?それとも…?
おととい → 昨日 → 今日という順番なので、混同しやすいですが、順序を意識しましょう。
「おとといの次の日」は「昨日(きのう)」にあたります。特に子どもや日本語学習者にとっては、時間の流れを言葉で把握することが難しい場合もあります。
「一昨日(おととい)は2日前」「昨日は1日前」といった数え方を一緒に確認しながら教えると理解が深まります。また、スケジュールや予定を確認する際には、「○日前」「○日後」という数値で示すと、より正確に共有できるでしょう。
子どもに教えるときのポイントと覚え方

リズムや繰り返しで楽しく覚える方法
「明日・明後日・明々後日」などの表現は、繰り返しやリズムを使って覚えると混乱しにくくなります。
たとえば、「今日、明日、明後日、明々後日」と声に出してリズムよく唱えたり、手拍子やステップを踏みながら言葉を繰り返すと、体に染み込むように自然と覚えることができます。
特に子どもには、歌やゲーム形式で覚えさせる方法が効果的です。「今日はなに?」「その次は?」といったクイズ形式で繰り返すことで、楽しみながら日付の感覚を身につけられます。
また、カレンダーや予定表にシールを貼ったり、色分けしたりすることで、視覚的に覚えやすくする工夫もおすすめです。
よくある間違いとその理由
「明後日」と「明々後日」を逆に覚えてしまうことが多いので、しっかり繰り返して確認するのがおすすめです。
たとえば、「あさって」と「しあさって」は音の響きが似ているため、特に幼児や日本語学習者にとっては区別がつきにくく感じることがあります。また、日常生活で「しあさって」までの予定を頻繁に立てることが少ないため、実際に使う機会が減ってしまい、混同しやすくなってしまいます。
そういった場合には、「あさっては2日後」「しあさっては3日後」といった数の感覚と結びつけて覚える方法が有効です。カレンダーに日数を数えながら確認することで、視覚と体感の両方から理解を深めることができます。
実生活で役立つ!日付の伝え方テクニック

「◯日後」「◯日前」でスマートに伝える
「明日」「明後日」「明々後日」などの言葉は日常会話でよく使われますが、相手によっては混乱を招くこともあります。特に年齢や文化背景の異なる相手と話す場合、具体的な日数で伝えるほうが明確です。
たとえば、「明々後日」は「3日後」と言い換えることで、直感的に理解してもらいやすくなります。また、「おととい」や「さきおととい」なども、「2日前」「3日前」と表現すれば、より客観的かつ論理的に伝わります。特にスケジュール調整や予定の相談では、こうした言い換えを活用することで、誤解やすれ違いを防ぐことができます。
ビジネスやメールでの表現例
ビジネスの場面では、あいまいな表現を避けることが重要です。「しあさって」などの口語表現は、メールや社内文書には不向きな場合があります。代わりに、「8月10日(水)」や「〇日後」といった具体的な日付を用いることで、相手に正確な情報を伝えることができます。
また、「翌々日」や「翌営業日」といったビジネス用語を活用するのも効果的です。特に納期や締め切りなど、時間に関するやり取りでは、正確で誤解のない表現を心がけましょう。
地域によって異なる言い方があるって本当?

関西と関東での表現の違い
「やのあさって」などは関西方面で使われることが多い傾向があります。これは、関西地方特有の言語感覚やリズムに由来しており、世代を問わず一定の使用率があります。
関東地方ではあまり聞かれない表現であるため、関東出身の人にとっては意味が伝わらない場合もあります。
逆に、関東では「明日」「明後日」「明々後日」といった標準語的な言い回しが主流であり、それ以降の日付を示すときには「◯日後」などの具体的な表現を用いることが多いです。このように、地域ごとに表現の文化が異なることは、日本語の豊かさの一例といえるでしょう。
方言によるバリエーション
地方によっては「ししおととい」や「やのおととい」などユニークな言い方があります。これらの表現は、特定の地域や家庭で長年使われてきたもので、標準語ではあまり見かけません。
「ししおととい」は「4日前」や「5日前」を指す場合があり、使う人や場所によって意味が若干異なることもあるため、注意が必要です。
「やのおととい」も同様に、日付感覚のずれが生じやすい表現のひとつです。これらの言い回しは、昔ながらの会話に味わいを添える反面、現代の会話では誤解を生みやすいことから、補足説明をつけたり、文脈から意味を汲み取る力が求められます。
まとめ|ややこしい日付の呼び方も、仕組みを知ればスッキリ!
- 基本は「今日」を中心に、未来・過去へと日数を数えるだけなので、仕組みがわかれば難しくありません。
- 地方によって呼び方に大きな違いがあり、同じ言葉でも意味が異なるケースがあるため、地域差には特に注意が必要です。
- 方言表現(やのあさって・ししおととい等)は、家族や友人同士では通じても、他の地域では混乱を招くことがあるため、使い方を工夫しましょう。
- 子どもや高齢者との会話では、「3日後」「2日前」といった数値での説明がとても効果的。具体的な日付での伝達や、カレンダー・図解を活用するのもおすすめです。
- ビジネスの場面では特に曖昧な言い方を避け、日付や曜日で伝えるように心がけましょう。
混乱しやすい「日付の呼び方」ですが、全体の構造や成り立ちを知ることで、自信を持って使い分けができるようになります。
この記事が、日常会話や子どもへの声かけ、ビジネスシーンでのやりとりなど、さまざまな場面で役立てばうれしいです。